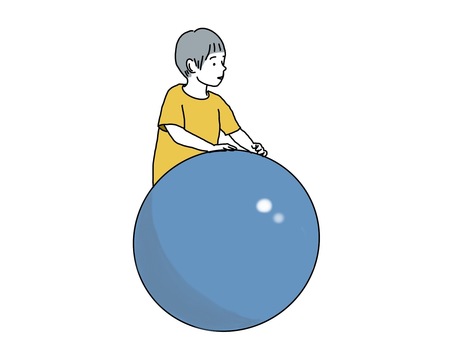
社内研修「感覚統合の発達と支援 ― 子どもの隠れたつまずきを理解する ―」 第4章~第5章
2025/09/03
本日は、増田修治先生による「感覚統合」についての研修を行いました。
今回は、前回に引き続き、A・ジーン・エアーズの名著『感覚統合の発達と支援』(金子書房)より、第4章~第5章を学びました。
療育現場に携わる者にとって、多くの学びと気づきにつながる時間となりました。
第4章 感覚統合機能不全とは何か 〜症状・原因・程度〜
感覚統合機能不全とは、脳内で必要な感覚情報がスムーズに処理されず、「交通渋滞」のように詰まってしまう状態を指します。
このため、脳のある領域が本来の役割を果たすために必要な情報を受け取れなくなり、発達や学習に影響が出ます。
症状は多様であり、学習障害や発達障害をもつ子どもでは、言語障害、問題行動、心理的問題を同時に抱えていることも少なくありません。
原因については、遺伝的要因、環境汚染物質や化学物質、有害ウイルスなどの影響が挙げられるものの、実際にははっきりと分かっていないのが現状です。
感覚統合は次のような段階を経て発達します。
1. 第一段階:触覚・固有受容覚・前庭覚・聴覚・視覚の入力
2. 第二段階:姿勢・バランス・筋緊張・重力への安心感・摂食・心地よさ
3. 第三段階:身体知覚・両側協調・運動プランニング・注意の持続・情緒の安定
4. 第四段階:言語・発話・手と目の協応・視知覚・目的ある活動
これらが統合されることで、【最終産物】として「集中力、組織化能力、自尊心、自己統制、学習能力、抽象思考、身体と脳の左右の特殊化」などが育まれていきます。
小学校入学前の統合段階のどこかで欠如や異常がある場合、学校での勉強や生活全般に欠如や異常も出てきます。
たいていの大人は、未成熟な感覚統合の最終産物しか見えていなく、様々な場面において子どもが問題行動を起こしているように感じてしまうことがあります。
ほとんどの子どもは悪いことをしたいとは思っていないが、感覚統合不全のある子どもを「悪い子」であるかのように扱い続ければ、それこそ、わざと問題行動を起こすようになりかねなくなります。
第5章 前庭系にかかわる障害 〜動きの感覚が各種スキルの発達に及ぼす影響〜
前庭系は、姿勢やバランスの制御だけでなく、眼球運動、注意の集中、運動スキル、学習の基盤をつくる重要な感覚システムです。
前庭受容器は胎児期から活動を始め、死ぬまで重力の影響を受け続けています。その働きは絶え間なく脳に情報を送り続け、神経系の他の機能との「調整」を行っています。
また、目と首の筋肉、筋肉や身体全体の動き、姿勢反応や平衡反応、情動発達や行動、さらには消化管の働きや学習にも関わっています。
前庭系の障害
一般に、学習や行動の妨げになる前庭系の障害には2種類あり、脳の前庭入力に対する反応が低いか、あるいは過剰に反応するかのどちらかである。
◎前庭系の低反応
前庭反応が低い子どもは、眼球運動や姿勢に影響が出やすく、身体の左右両側の統合に難があることが多く、左右を上手く強調させることができません。
また、前庭機能の低下に伴う発話障害なども見られます。前庭機能不全に加えて発話・言語障害のある子どもは、身体運動と運動プランニングにも困難があるのが普通です。
◎前庭系の過剰反応
前庭入力に対する過敏性は「重力不安」や「動きへの不耐性」として現れ、日常生活や遊びに支障をきたすことがあります。
・ 重力不安
重力不安のある子どもは、慣れない姿勢になったときや、そういう姿勢をとろうとしたとき、あるいは他の誰かが自分の動きや姿勢を制御しようとしたときに、恐怖や不安や苦痛を感じます。
・ 動きへの不耐性
前庭系の過剰反応のある子どもの中には、急速な動きや回転の動きをとても不快に感じる子どもがいます。必ずしも動きそのものがこわいのではなく、動きによって不快感が生じるのであります。
このように前庭系のはたらきは単なる身体のバランスにとどまらず、子どもの発達全体に深く関わっています。
まとめ
感覚統合の発達は、触覚や前庭覚などの感覚入力から始まり、段階的に運動、認知、情緒、学習へとつながっていきます。
しかし、一部の子どもは感覚統合に困難さを抱え、運動スキルの習得や触覚刺激への反応に影響が出る場合があります。
療育の現場で求められるのは、子どもの「感覚の特性」を理解し、その子が安心して挑戦できる環境を整えることです。
今後は子どもの行動を「困った行動」と見るのではなく、「感覚統合のつまずき」として理解する視点を持つ。行為機能不全のある子どもには、無理をさせず成功体験を積めるよう支援方法を柔軟に選択するようにしていきたいと思います。
講師
元白梅学園大学 教授 増田 修治先生(マリリンスポーツ塾Go 顧問)
参考文献
A・ジーン・エアーズ著
『感覚統合の発達と支援 ― 子どもの隠れたつまずきを理解する ―』(金子書房)
